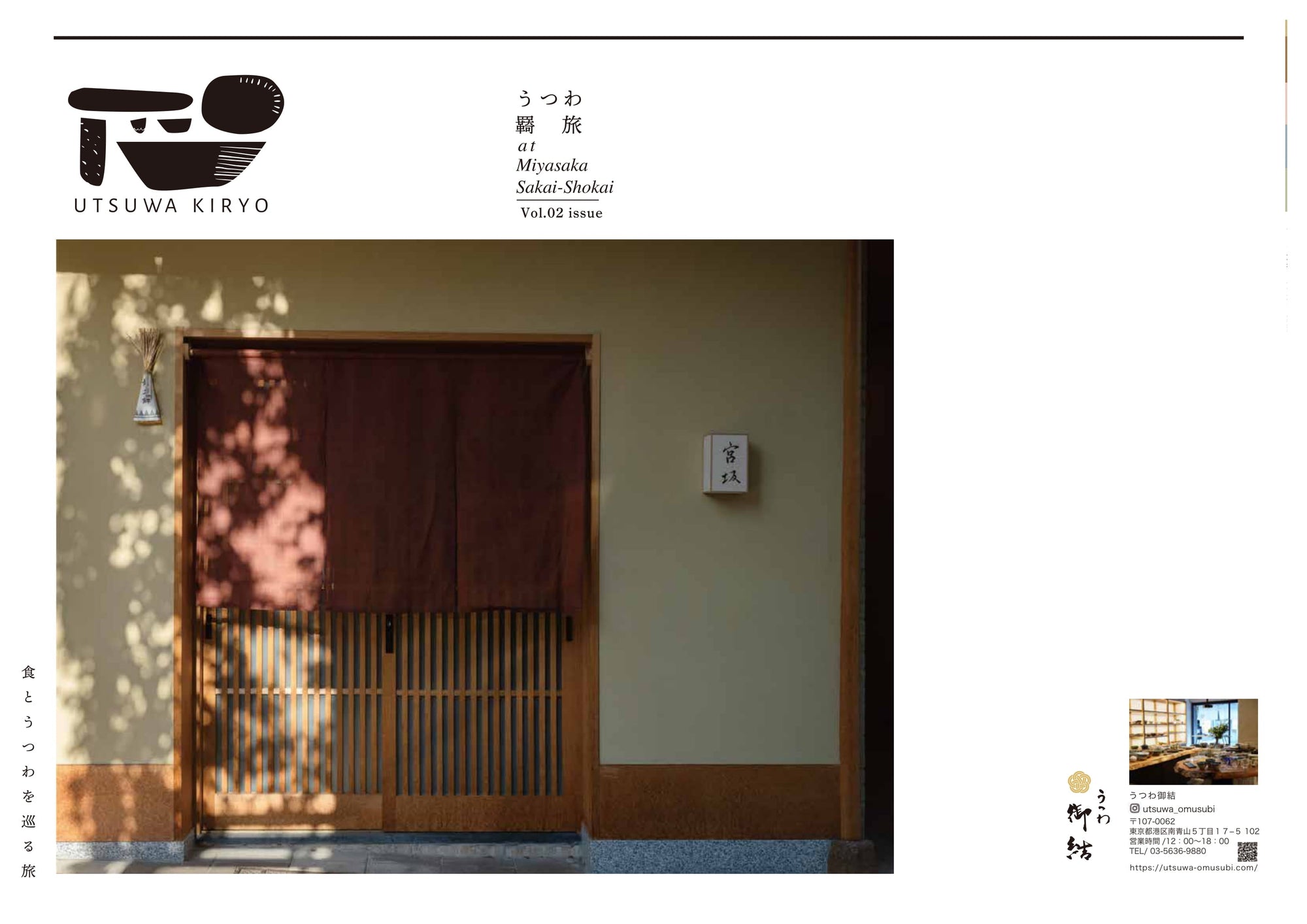さて、先日ご紹介した『うつわ羈旅vol.2』――本田直之さんを聞き手としてお迎えし、宮坂さん、酒井さんに器の選び方についてお話を伺った記事の英語版を作成しました。

日本語版の作成時から印刷用の記事作成を担当し、何度も何度も、何度も読み返し、推敲を重ねました。
インタビュー記事なので、私が大きく加筆することはありませんでしたが、本田さんが丁寧に引き出してくださったお二人の言葉の奥にある想いが、読み手さんにしっかりと伝わるように力を注ぎました。
器との出会いから、お客様へのおもてなしの心まで――
宮坂さんの言葉の端々からは、器そのものへの敬意と、そこに寄り添う感性が静かに、けれど確かに伝わってきました。
茶道のたしなみ、京都の料亭で培われた目と心。そうした背景があるからこそ、季節のうつろいを感じさせるしつらえや、空間そのものに宿る“もてなし”の気配に、私は何度も息を呑みました。

日本人がふと口にする「あ、いいな」という感覚。
それは誰もが心に持ちうるものかもしれませんが、それを他者へと手渡すには、知識やセンスはもちろん、細やかな気配りを惜しまない姿勢が必要なのだと、あらためて気づかされます。
そしてそれを、宮坂さんはまるで呼吸をするように、自然に実践されている。
以前『ようび』についてジャーナルを書いたとき、気づけば何度も宮坂さんの姿が思い浮かび、胸が熱くなったのを覚えています。器を通して見える世界の豊かさを、また一つ教えていただいたような気がしています。

そして、酒井さん。
器、食材、お酒、スタッフ――すべての存在に、背景ごと丁寧に目を向けるその姿勢に、何度もうなずかされました。
ただ「良いもの」を選ぶのではなく、それがどこから来て、誰の手を経てここにあるのかまでを大切にされている。そのまなざしは、単なる“選び手”ではなく、つくり手と共に歩む“つなぎ手”のようでもありました。

器に対する知識も想いも、自分は到底敵わないなぁと遠く感じながらも、
その語り口にふと作家さんたちの顔が浮かび、酒井さんの事をお話ししたら
「こんなふうに器を見てくれる人がいるんだ」と、きっと嬉しく思うだろうな、と、私まであたたかい気持ちになりました。
また、お話の端々からは、共に働くスタッフへの気配りや育成にも力を注がれていることが伝わってきて、思いやりが自然ににじむそのあり方に、酒井さんの懐の深さを感じました。
長々と私の話をしてしまいましたが、うつわを通じてさまざまな想いに触れられたことが嬉しくて、ぜひ皆様にもご覧いただけたらなと思っています。